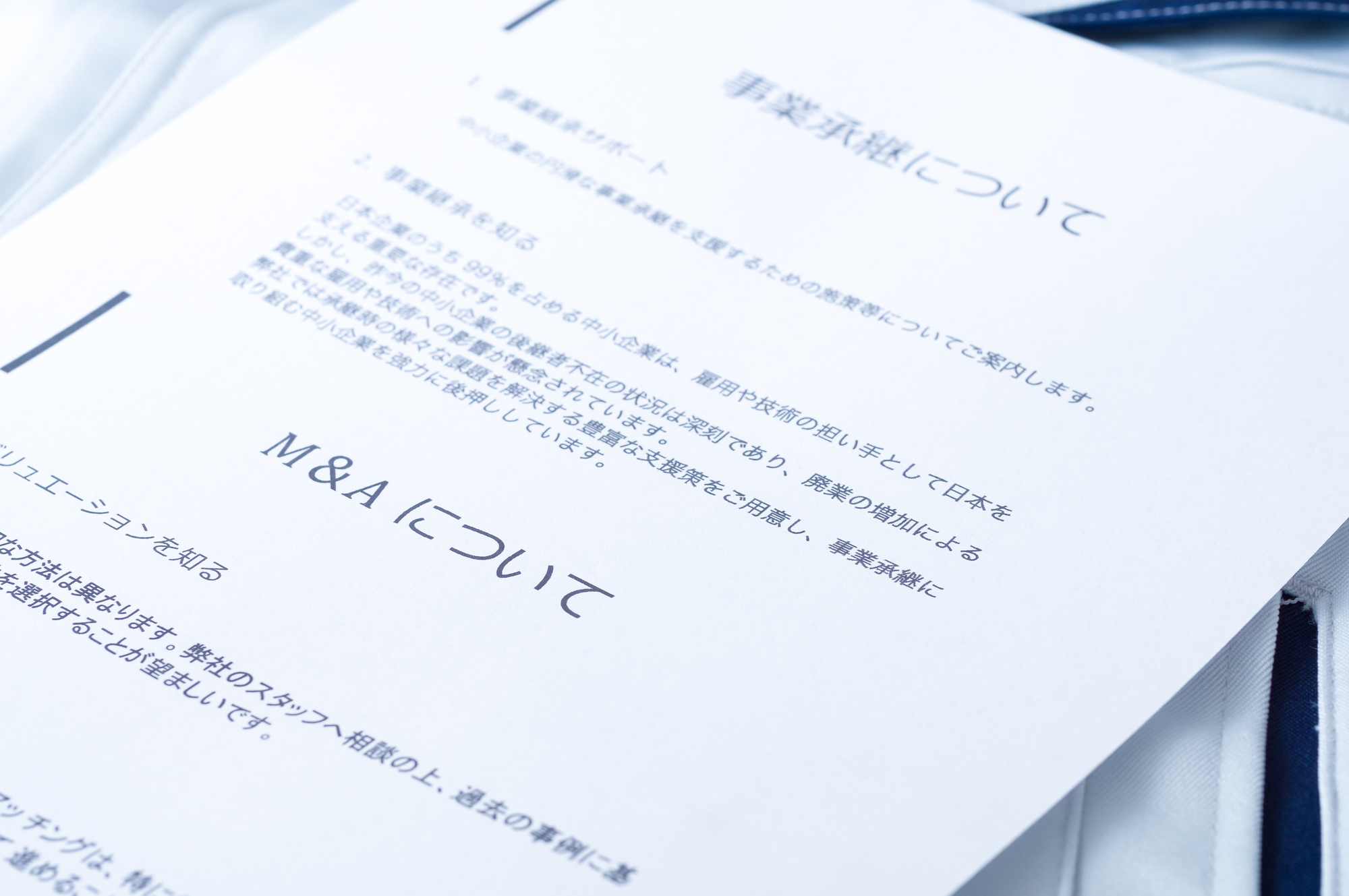
吸収合併においては、吸収される側の会社、吸収する側の会社のそれぞれがおこなわなければならない手続きがあります。そのうち今回は、吸収される側に視点を置いて、必要な手続きやその流れなどを詳しく解説していきます。
M&A・事業承継で失敗したくないなら
ジョブカンM&Aは、経験豊富なアドバイザーが事業の売却・買収をトータルでサポートします。
「信頼できる相手を見つけたい」「交渉や手続きが不安」「適正な価格で取引したい」といった、M&Aに関するあらゆるお悩みを解決に導きます。
詳しいサービス内容を知りたい、気軽に相談したいという方は、下記サービスサイトをご覧ください。
- 吸収合併とは
- 会社の合併方法には、「吸収合併」のほかに「新設合併」もある
- 吸収合併をおこなう理由
- 【消滅会社】デューデリジェンスと簿外債務リスクへの対応
- 吸収合併において消滅会社がおこなう手続きの流れ
- 吸収合併において消滅会社がおこなう手続きと存続会社がおこなう手続きの違い
- 消滅会社の従業員への対応は?
- 吸収合併後の消滅会社の決算はどうすればいい?
- FAQ|吸収合併・消滅会社に関するよくある質問
- 吸収合併を成功させるためには消滅会社・存続会社双方が自社の役割と責任を理解することが大切
吸収合併とは
まずは、吸収合併という言葉の意味から確認していきましょう。
吸収合併とはM&Aの一種です。具体的には、複数の会社を既存の1つの会社に吸収させて、権利義務のすべてを引き継ぐスキームです。会社法第2条27号においては、次のように定義されています。
「会社が他の会社とする合併であって、合併によって消滅する会社の権利義務の全部を、合併後、存続する会社に承継させるものをいう」
吸収合併においては、吸収される側の会社は「消滅会社」、吸収する側の会社は「存続会社」と呼ばれます。つまり、前者が売り手企業、後者が買い手企業ということになります。
吸収合併を実施すると、消滅会社の株式の代わりに存続会社の株式が交付されて、消滅会社の株主は存続会社の株主になります。ただし、存続会社の株式の代わりに、消滅会社の株主に対して金銭などを交付することも可能とされています。
| 項目 | 消滅会社 | 存続会社 |
| 法的地位 | 合併によって法人格が消滅する | 合併後も法人格を維持して、事業を継続する |
| 権利義務 | すべての権利義務が存続会社に承継される | 消滅会社の権利義務を包括的に承継する |
| 株主 | 消滅会社の株主は、合併比率に応じて存続会社の株式または金銭などを受け取る | 存続会社の株主は、合併後も株主としての地位を維持する |
| 従業員 | 原則として、従業員は存続会社に転籍する | 消滅会社の従業員を受け入れて、雇用を継続する |
| 会計処理 | 合併に伴い、資産・負債を清算して、会計帳簿を閉鎖する | 消滅会社の資産・負債を引き継ぎ、会計処理をおこなう |
消滅会社とは
消滅会社は、吸収合併において自社の権利義務をすべて譲渡するため、法人格が無くなります。しかし、吸収合併においては、存続会社側の企業規模が大きかったり業績が好調だったりするため、吸収合併によって経営が安定しやすくなるなどのメリットがあります。
また、後継者が見つからないという問題を抱えていた会社にとっては、後継者探しをする必要がなくなることも大きなメリットとなり得ます。
存続会社とは
存続会社は、吸収合併を実施することで、消滅会社の権利義務をすべて引き継ぐことになります。
“権利義務すべて”なので、資産も負債も引き継ぐということになりますが、経営資源や人材を獲得できるうえ、販路の拡大や新規事業への進出なども実現しやすくなるため、メリットが大きいといえます。
また、決算書上で事業規模を大きく見せられるうえ、株主を含めた投資家の期待値が高ければ、株価の値上がりも期待できます。
M&A・事業承継で失敗したくないなら
ジョブカンM&Aは、経験豊富なアドバイザーが事業の売却・買収をトータルでサポートします。
「信頼できる相手を見つけたい」「交渉や手続きが不安」「適正な価格で取引したい」といった、M&Aに関するあらゆるお悩みを解決に導きます。
詳しいサービス内容を知りたい、気軽に相談したいという方は、下記サービスサイトをご覧ください。
会社の合併方法には、「吸収合併」のほかに「新設合併」もある
会社の合併方法には、先に解説した「吸収合併」のほかに、「新設合併」というスキームもあります。この2つにどんな違いがあるかというと、前者においては、存続会社以外のすべての会社の法人格が消滅することになる一方、後者は、存続会社というもの自体存在せず、合併されるすべての会社の法人格が消滅することになります。代わりに、新しい会社を設立して、法人格が消滅するすべての会社の権利義務を引き継ぐことになります。
その他の主な違いは次の表の通りです。
| 吸収合併 | 新設合併 | |
| 法人格 | 存続会社の法人格のみ残り、他のすべての会社の法人格が消滅する | すべての会社の法人格が消滅する |
| 権利・義務の承継 | 存続会社が承継 | 新会社が承継 |
| 許認可の承継 | 存続会社が承継 | 承継できないため、新規に取得するか、もしくは引き継ぎの手続きをおこなう必要がある |
| 上場の維持 | 可能 | 不可。新規上場の申請をおこなう必要がある |
| 株主への交付 | 株式・社債・現金 | 株式・社債など |
| 登録免許税の算出 | 「増加資本金の額の1000分の1.5」であり、かつ「その増加資本金の額が、消滅会社の資本金等の額を下回る場合は、その差額の1000分の1.5」 | 資本金×0.15% |
| 効力発生日 | 契約で定めた日。登記は効力発生から2週間以内におこなう | 会社設立日。登記は効力発生と同時におこなう |
上記の違いからわかる通り、新設合併においては、新設会社は事業に必要な許認可を承継できないうえ、上場も維持できないため、手続きが煩雑になります。そのため、吸収合併と比べると実施されにくい傾向にあります。
M&A・事業承継で失敗したくないなら
ジョブカンM&Aは、経験豊富なアドバイザーが事業の売却・買収をトータルでサポートします。
「信頼できる相手を見つけたい」「交渉や手続きが不安」「適正な価格で取引したい」といった、M&Aに関するあらゆるお悩みを解決に導きます。
詳しいサービス内容を知りたい、気軽に相談したいという方は、下記サービスサイトをご覧ください。
吸収合併をおこなう理由
では、吸収合併がおこなわれる理由は何かというと、主な理由は次の通りです。
それぞれ詳しくみていきましょう。
短期間で新しい事業を立ち上げるため
販路や業務の流れが確立している会社を吸収合併すると、存続会社は短期間のうちに新しい事業をスタートすることができます。
また、吸収合併においては、資産や負債、契約関係、雇用契約などを個別に転移する必要がなく、存続会社は消滅会社のすべての権利義務を包括的に引き継ぐことができるため、手続きがスムーズという意味でも、新しい事業を短期間で立ち上げやすいといえます。
低コストで会社を成長させるため
吸収合併においては、存続会社は消滅会社への対価を、存続会社の株式とすることができるため、現金を調達して支払った場合と比べて、利息の支払いが発生することがないぶん、コストを抑えることが可能です。
シナジー効果を得るため
消滅会社と存続会社の経営資源が掛け合わされることによって、シナジー効果を獲得しやすくなります。シナジー効果を反映させた商品やサービスを開発すると、企業の成長につながりやすくなります。
事業承継のため
吸収合併においては、存続会社が消滅会社の権利・債務・従業員などを引き継ぐことになるため、後継者が見つからない消滅会社にとってはメリットが大きいスキームであると考えられます。
吸収合併によって、自社よりも経営体制がしっかりしている会社に自社の運営を任せられることになるため、事業承継目的で吸収合併を実施する企業は多いです。
M&A・事業承継で失敗したくないなら
ジョブカンM&Aは、経験豊富なアドバイザーが事業の売却・買収をトータルでサポートします。
「信頼できる相手を見つけたい」「交渉や手続きが不安」「適正な価格で取引したい」といった、M&Aに関するあらゆるお悩みを解決に導きます。
詳しいサービス内容を知りたい、気軽に相談したいという方は、下記サービスサイトをご覧ください。
【消滅会社】デューデリジェンスと簿外債務リスクへの対応
合併契約の締結、株主総会での承認といった法的な手続きに進む前に、**デューデリジェンス(DD)**への対応という、売り手企業にとって非常に重要なプロセスがあります。
デューデリジェンス(DD)の重要性
デューデリジェンスとは、買い手企業が売り手企業の価値やリスクを詳細に調査するプロセスです。財務、法務、事業、税務、人事など多岐にわたる項目について、買い手から膨大な資料の提出を求められます。この調査で、**貸借対照表には計上されていない潜在的な負債(簿外債務)**や、訴訟、労働問題などの隠れたリスクがないかを徹底的に洗い出されます。
簿外債務と表明保証
簿外債務の代表例は、未払いの残業代、退職給付引当金、係争中の訴訟費用、環境汚染対策費用などです。これらの負債は合併後に存続会社がすべて引き継ぐことになるため、買い手にとってはM&Aの失敗に直結しかねない重大なリスクとなります。
そのため、合併契約書には**「表明保証」**という条項が盛り込まれるのが一般的です。これは、「開示された情報や財務諸表が真実かつ正確であること」を売り手側が買い手に対して保証するものです。もし表明保証に違反し、合併後に簿外債務が発覚した場合は、売り手は買い手から損害賠償を請求されるリスクがあります。
売り手は、DDで質問された際は不都合な情報であっても正直に回答し、表明保証の範囲を買い手と十分に交渉することが不可欠です。
吸収合併において消滅会社がおこなう手続きの流れ
続いては、吸収合併において消滅会社がとる手続きの流れをみていきます。必要な手続きは、基本的には次の通りです。
合併契約書を作成する
取締役会決議をおこなう
合併契約を締結する
合併契約書の事前開示をおこなう
株主総会で合併の承認を受ける
債権者保護手続きをおこなう(官報公告および個別催告)
反対株主の株式買取請求に対応する
吸収合併の効力が発生する
登記手続きをおこなう
それぞれ詳しくみていきましょう。
合併契約書を作成する
吸収合併を実施することが決まったら、合併契約書を作成して締結をおこないます。合併契約書には、会社法第七百四十九条に基づき、次の事項をまとめます。
一 株式会社である吸収合併存続会社および吸収合併により消滅する会社の商号および住所
二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社の株主または持分会社である吸収合併消滅会社の社員に対してその株式または持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭などについての次に掲げる事項
イ 当該金銭などが吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)またはその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金および準備金の額に関する事項
ロ 当該金銭などが吸収合併存続株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)であるときは、当該社債の種類および種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法
ハ 当該金銭などが吸収合併存続株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)であるときは、当該新株予約権の内容および数またはその算定方法
ニ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項および当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容および数もしくは額またはこれらの算定方法
三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社および吸収合併存続株式会社を除く)または吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く)に対する同号の金銭などの割当てに関する事項
四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権または金銭についての次に掲げる事項
イ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容および数またはその算定方法
ロ イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類および種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法
ハ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額またはその算定方法
五 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権または金銭の割当てに関する事項
六 吸収合併がその効力を生ずる日(効力発生日)
なお、合併契約書を作成する前に、合併条件に関して十分に話し合うことは不可欠で、契約書を作成した段階で、条件に関しては合意がとれていなければなりません。
取締役会決議をおこなう
合併契約書を作成したら、契約を締結する前に、それぞれの会社で正式な意思決定および承認をおこなう必要があります。具体的には、取締役会で決議することになります。
合併契約を締結する
取締役会で決議がとれたら、合併契約書を締結します。
合併契約書の事前開示をおこなう
株主や債権者などから合意に関しての承認を得るか、得られない場合、異論を申し出る機会を与える必要があるため、契約内容の事前開示をおこないます。合意契約内容の事前開示は、書類でおこなうため、書類を用意する必要があります。
株主総会で合併の承認を受ける
吸収合併は組織再編行為であり、吸収合併実施後は会社の組織が大きく変わってしまうため、株主総会において吸収合併の承認を受けなければなりません。承認を得るタイミングは、合併契約書で定めた効力発生日の前日までです。
株主総会は、基本的には特別決議を実施することになります。特別決議とは、議決権を持つ株主の過半数が出席して、出席した株主の3分の2以上の賛成によって承認される決議方法です。株主は、前述した事前に開示された書類や、あるいは株主総会の招集通知などをもとに、合併可否について判断します。
ただし、株主の承認について要件を満たしている場合、株主総会の開催を省くことができます。特別決議なしで合併を実施した場合、「簡易合併」となります。
債権者保護手続きをおこなう(官報公告および個別催告)
債権者を保護するため、会社法に基づき、「①官報への公告」「②把握している債権者への個別の催告」の両方が必要です。公告・催告では、合併に異議があれば1ヶ月以上の期間内に申し出るべき旨などを記載します。債権者から異議があった場合、会社は弁済、担保の提供、または財産の信託などの対応をとる必要があります。
反対株主の株式買取請求に対応する
反対株主の株式買取請求とは、合併に反対している株主が保有している株式を、会社に対して買い取るように請求できる権利を意味します。
株式の買取価格に関しては、会社と、吸収合併に反対する株主とで相談します。もし、協議で決定できない場合には、裁判所の決定に従います。
吸収合併の効力が発生する
事前に設定した効力発生日を迎えると、存続会社は消滅会社の権利義務をすべて引き継ぐことになります。なお、吸収合併に必要な手続きは、効力発生日までにすべて終わらせておくことが必要で、終わらせられなかった場合、効力が発生しないことになります。
効力発生日を迎えたら、事前開示書類は、必要なときにいつでも使えるようしっかり保管します。
登記手続きをおこなう
効力発生日から2週間以内に、吸収合併に関する登記手続きをおこないます。
登記手続きの内容は、消滅会社の場合は「解散登記」、存続会社の場合は「変更登記」となります。
前者の場合、次のような書類を準備する必要があります。
また、解散登記の登録免許税として3万円が必要です。
M&A・事業承継で失敗したくないなら
ジョブカンM&Aは、経験豊富なアドバイザーが事業の売却・買収をトータルでサポートします。
「信頼できる相手を見つけたい」「交渉や手続きが不安」「適正な価格で取引したい」といった、M&Aに関するあらゆるお悩みを解決に導きます。
詳しいサービス内容を知りたい、気軽に相談したいという方は、下記サービスサイトをご覧ください。
吸収合併において消滅会社がおこなう手続きと存続会社がおこなう手続きの違い
先に説明した通り、前述の吸収合併の手続きは消滅会社がおこなうものです。
存続会社がおこなう手続きの流れも、大まかには同じですが、吸収される側とする側であることから、いくつかの点において違いがあります。具体的には次の通りです。
事前に開示する情報
株主への対応
効力発生日以降に承継される権利義務に関する手続き
事後開示手続き
それぞれ詳しくみていきましょう。
事前に開示する情報
前述の通り、合併契約を締結したら、合意契約内容の事前開示をおこないますが、消滅会社と存続会社では事前開示情報の書類に記載する内容が異なります。もっとも大きな違いは、合併対価の相当性に関する事項です。
合併対価の相当性とは、「どのような前提で合併における買取対価を決定したか」を指します。なぜ、合併対価の相当性を開示するかというと、株主や債権者が意思決定をおこなう際、合併対価の相当性を参考にして、合併を認めるかどうか判断するためです。
合併対価を算出した前提については、消滅会社、存続会社ともに書類に記載する必要がありますが、これに加えて、消滅会社は合併対価を決定した方法についても詳細を示すことが大切です。
株主への対応
球種合併を実施するためには、消滅会社と存続会社の両方の株主の承認を得ることが不可欠です。そのために必要な手続きは次の通りです。
上記のうち、消滅会社と存続会社とで必要な手続きが異なるものと同じものがありますが、言葉の意味の説明も含めて、一つずつ解説していきます。
反対株主の株式買取請求権
反対株主への株式買取請求は、消滅会社、存続会社ともにおこなう必要があります。
先に解説した通り、吸収合併に反対する株主は、会社に対して株式の買取請求をおこなうことが認められていますが、買取請求は、効力発生日の20日前から前日までの間に実施することが定められています。
【消滅会社のみ】新株予約権買取請求
消滅会社の新株予約権者は、吸収合併によって新株予約権を失います。
この際、新株予約権が承継される旨とその条件が定められているものの、条件に合致する新株予約権の承継がなされなければ、新株予約権買取請求権が発生することになります。
登録株式質権者への対応
登録株式質権者とは、株主名簿に氏名、住所、質権の目的となる株式が記載・記録されており、株式に対する質権を設定した者のことです。登録株式質権者は、株主同様、吸収合併の影響を受けるため、官報公告や個別催告をおこなって、吸収合併を実施することを告知する必要があります。
登録新株予約権質権者への対応
登録新株予約権質権者とは、新株予約権に質権登録、設定している人を意味します。登録株式質権者への対応同様、官報公告や個別催告の実施によって情報を開示する必要があります。
【消滅会社のみ】株券提供公告
株券提供公告とは、合併を実施するために、保有している株券の提供をおこなうことを知らせるための広告で、消滅会社が実施する必要があります。
ただし、定款で株券の不発行を定めている企業に関しては、株券が存在しないため、株券提供公告は必要ありません。また、非公開会社に関しては、株主名簿に株券不所持の申し出があると記載することによって、株券提供公告の代わりとすることができます。
効力発生日以降に承継される権利義務に関する手続き
消滅会社が所持している不動産は存続会社に引き継がれるため、不動産の権利を移転するために移転登記をおこなう必要があります。なお、存続会社に引き継がれるタイミングは効力発生日です。そのため、効力発生日以降に移転登記をおこなって、登記を存続会社に変更するという流れになります。
同じく効力発生日以降に、消滅会社が有している銀行口座の名義を、存続会社の名義に変更する必要があります。名義変更が遅くなると、振込が必要なときなどに対応できなくなることがあるので注意しましょう。
事後開示手続き
事後開示手続きは、存続会社にのみ必要とされる手続きです。手続きをおこなうのは効力発生日から6か月以内で、会社法施行規則第200条によって定められた次の事項を開示する必要があります。
消滅会社の従業員への対応は?
続いては、吸収合併後の、消滅会社の従業員への対応をみていきましょう。
雇用契約
会社法第750条に基づき、消滅会社の重量院の雇用契約は継続されます。吸収合併を理由とする解雇やリストラは、基本的にはおこなわれることがありません。
労働条件
消滅会社の権利義務は、吸収合併においては承継されるため、給与や福利厚生などの労働条件も基本的には引き継がれます。ただし、たとえば給与に関して、消滅会社と存続会社の2つの給与体系が存在したままだと不便が生じるため、存続会社の給与体系へとシフトされていくことになります。吸収合併後の企業再編によって、配置転換などが実施されるケースもあります。退職金制度についても同様です。
ただし、存続会社の制度に統一する際、消滅会社の従業員にとって労働条件が不利益に変更される場合は注意が必要です。給与や退職金規定などの重要な労働条件を引き下げるには、原則として従業員からの個別の同意が求められます。一方的な不利益変更は、後に労働問題へ発展するリスクがあるため、慎重なすり合わせや、不利益を緩和するための経過措置などを設けることが極めて重要です。
社会保険
吸収合併においては、存続会社が社会保険の資格取得届を提出して、消滅会社から受け入れる従業員の健康保険被保険者証を発行します。通常、日本年金機構による審査完了日から2営業日後に保険証が発行されます。
雇用保険
雇用保険の手続きに関しては、消滅会社、存続会社の双方が「同一事業主の認定手続き」をおこなうことが望ましいといえます。
なぜかというと、消滅会社からいったん退職してから存続会社に入社するなどしてしまうと、雇用保険を受け取れなくなったり、金額が少なくなったりする可能性があるためです。
労働保険
消滅会社と存続会社の事業が同じで、消滅会社を存続会社の営業所などにする場合、労働保険成立の手続きと継続事業一括手続きが必要になります。
なお、吸収合併によって労働保険料が大幅に増額となることが見込まれる場合、増加概算保険料の申告および納付も必要になります。
従業員への丁寧な情報開示とケア
吸収合併の際、従業員は「自分の雇用はどうなるのか」「給料や福利厚生は変わるのか」といった大きな不安を抱えます。法的・制度的な手続きはもちろん重要ですが、従業員の不安を解消するためのコミュニケーションも、合併成功には欠かせない要素です。
情報開示のタイミングと内容
従業員への情報開示は、合併の基本合意が固まった後など、適切なタイミングで実施します。合併の目的、合併後の会社のビジョン、そして最も重要な**従業員の処遇(給与、福利厚生、役職、人事制度)**について、丁寧かつ具体的に説明することが不可欠です。
コミュニケーションの場を設ける
合併に関する説明会を開催し、会社のトップや担当者から直接伝える場を設けることが望ましいでしょう。質疑応答の時間を設けることで、従業員の疑問や懸念に真摯に対応する姿勢を示すことが、信頼関係の構築につながります。
不利益変更への対応
特に給与や退職金規定など、従業員にとって不利益となる労働条件の変更については、労働組合や従業員の代表と協議を重ね、個別の同意を得るプロセスが必須です。一方的な変更は労働問題に発展するリスクがあるため、慎重な対応が求められます。
吸収合併後の消滅会社の決算はどうすればいい?
吸収合併における消滅会社は、会社法第471条4号によって、解散すると定められています。会社が解散した場合、原則としては清算手続きをおこなうことになりますが、吸収合併によって解散した場合に関しては、会社法475条1号によって、清算が不要であるとされています。
つまり、消滅会社は吸収合併の効力発生日に解散して、法人格を失うということになります。
消滅会社の「解散事業年度」に係る確定申告と納税
消滅会社が解散した場合、吸収合併が実施された日の前日までの期間が事業年度とみなされます。この事業年度は、法人税法14条2号によって「解散事業年度」と呼ばれていますが、解散事業年度に係る確定申告と納税は、吸収合併が実施された日から2か月以内におこなわなければならないことが、法人税法74条および77条によって定められています。
なお、確定申告および納税をおこなうのは存続会社です。法人税法において、「合併により消滅した法人の確定申告書は、存続法人が提出する」と規定されています。
FAQ|吸収合併・消滅会社に関するよくある質問
続いては、吸収合併に関するよくある質問とその答えをみていきます。
許認可・税務
Q. 許認可の承継について注意すべきことはありますか?
吸収合併における許認可の引き継ぎは「法律ごとに承継可否が違う」ため、事業ごとに主管官庁へ事前確認が必須です。承継できない場合は、新規申請のタイミングを合併と合わせて調整する必要があります
許認可の取扱いに関する基本ルール
許認可は原則として「法人固有」のもの
個別法の規定によって承継できるかどうかが異なる
承継の可否の具体例
承継可能なケース(例)
承継できず、新規取得が必要なケース(例)
実務上の注意点
合併前に必ず主管官庁・自治体へ相談
承継不可の場合のリスク管理
官報公告・契約先への説明
費用・期間
Q. 繰越欠損金の引継ぎは可能?(適格合併と非適格合併)
消滅会社の繰越欠損金を存続会社が引き継げるかどうかは、その吸収合併が税法上の「適格合併」に該当するか「非適格合併」に該当するかで結論が全く異なります。
原則、繰越欠損金の引継ぎは可能です。適格合併と認められるには、対価が株式のみであることや、支配関係・事業の継続が見込まれることなど、複数の厳しい要件を満たす必要があります。これらの要件を満たせば、消滅会社の繰越欠損金は存続会社に引き継がれ、将来の課税所得と相殺できます。
繰越欠損金の引継ぎはできません。適格合併の要件を満たさない合併の場合、繰越欠損金を引き継ぐことはできません。
【注意】適格合併でも引継ぎが制限されるケース
適格合併であっても、租税回避を防ぐ目的で、引継ぎが制限される場合があります。たとえば、支配関係が生まれてから5年以内に合併がおこなわれ、かつ「みなし共同事業要件」を満たさない場合などです。このようなケースでは、引き継げる欠損金の額が制限されるため、必ず税理士などの専門家へ事前に相談することが不可欠です。
Q. 吸収合併の費用はどれくらいかかる?
吸収合併の費用の目安は次の通りです。
具体的な費用は次の通りです。
1. 登記関係費用
存続会社の資本金が増加する場合、その増加額 × 0.7%が登録免許税です。金額としては最低15万円になります。増資を伴わない場合はかからないこともあります。
また、司法書士報酬として5万~20万円程度かかります。
2. 専門家報酬
弁護士・会計士・税理士
スキーム検討、契約書作成、デューデリジェンス、税務申告などを弁護士・会計士・税理士に依頼した場合にかかる費用です。
中小規模(親子会社間やグループ内再編)の場合は50万~200万円程度で、上場会社やM&A案件規模が大きい場合は数百万円~数千万円に上ることもあります。
3. 税務申告関連費用
吸収合併に伴う確定申告・別表作成などです。顧問税理士に依頼する場合、通常顧問料+50万~100万円程度が目安となります。
4. 官報公告・公告費用
合併公告を官報に掲載する費用として、約3~4万円かかります。債権者保護手続きなどのために必要な費用です。
5. システム・実務統合作業コスト
会計システム・人事給与・基幹システムの統合費用です。数十万円~数百万円規模ですが、大企業だと数千万円単位になることもあります。
6. その他
その他、次のような費用が掛かることがあります。
Q. 吸収合併の手続きにかかる期間の目安は?
一般的には3か月~6か月程度かかります。ただし、上場企業や大規模M&Aの場合、半年~1年以上かかることがあります。各フローの期間の目安は次の通りです。
1.事前準備(1~2か月)
規模が大きいと調査に時間がかかり、2か月以上になることもあります。
2.株主総会・公告手続き(1~2か月)
※最低1か月間の異議申述期間が必要
3.合併効力発生日までの準備(1か月程度)
4. 合併効力発生日 → 登記(数日~2週間)
手続き上の留意点
Q. 議決権の3分の2以上の同意が得られない場合はどうなる?
議決権の3分の2以上の同意が得られない場合、合併契約は承認されず、合併は成立しません。取締役会で決議していても、株主総会で必要な賛成を得られなければ効力はありません。つまり、吸収合併自体が不成立ということになります。
これを回避するための対策としては次のようなことが考えられます。
1.事前調整
大株主や主要株主と事前に十分な合意形成をおこないます。ただし、同族会社やオーナー企業では株主持分を事前に固めやすいですが、持株比率が分散している場合は調整が難航しやすいです。
2.議決権割合の見直し
新株発行や自己株式の処分などによって賛成比率を確保する方法もありえますが、手続きや公正性に注意が必要です。
3.簡易合併・略式合併の利用
一定の要件を満たす場合、株主総会決議を省略できるケースがあります。たとえば、存続会社が消滅会社の議決権90%以上を保有している場合、「略式合併」ということになります。
Q. 略式合併・簡易合併とは?
略式合併と簡易合併は、いずれも株主への影響が限定的である場合に、株主総会の特別決議を省略できる制度です。
1. 略式合併(特別支配関係がある場合)
一方の会社が他方の会社の議決権の90%以上を保有している場合、被支配会社側(子会社など)の株主総会を省略できます。
例: 親会社(存続会社)が子会社(消滅会社)を吸収合併する場合、子会社側の株主総会が不要になります。
2. 簡易合併(合併対価が小規模な場合)
合併に際して消滅会社の株主に交付する財産(株式や金銭など)の価値が、存続会社の純資産額の20%以下である場合、存続会社側の株主総会を省略できます。
例: 大企業(存続会社)が小規模な会社(消滅会社)を吸収合併する場合、大企業側の株主総会が不要になります。消滅会社側では、原則通り株主総会が必要です。
Q. 専門家(弁護士・会計士など)にはどのタイミングで相談すべき?
専門家に相談すべき理想のタイミングは次の通りです。
吸収合併を成功させるためには消滅会社・存続会社双方が自社の役割と責任を理解することが大切
吸収合併を成功せるためには、消滅会社・存続会社の双方が、自社の役割と責任を理解することが非常に大切です。消滅会社にとっては、組織が無くなるスキームではありますが、存続会社として続いていくことになるため、新たな成長の機会ととらえて、お互いにとって良い結果が出せるよう、きちんと準備をすすめてくださいね。
M&A・事業承継で失敗したくないなら
ジョブカンM&Aは、経験豊富なアドバイザーが事業の売却・買収をトータルでサポートします。
「信頼できる相手を見つけたい」「交渉や手続きが不安」「適正な価格で取引したい」といった、M&Aに関するあらゆるお悩みを解決に導きます。
詳しいサービス内容を知りたい、気軽に相談したいという方は、下記サービスサイトをご覧ください。
この記事は、時点の情報を元に作成しています。

執筆 ジョブカンM&A編集部
ジョブカンM&Aは、株式会社DONUTSが運営するM&Aアドバイザリーサービスです。主に企業の事業承継、成長戦略、出口戦略(イグジット)といった多様なニーズに応えることを目的としています。最大の特徴は、累計導入社数20万社以上を誇るバックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」の広範なネットワークを活用している点です。この強力な顧客基盤を生かし、効率的なマッチングを実現します。
他の関連記事はこちら



