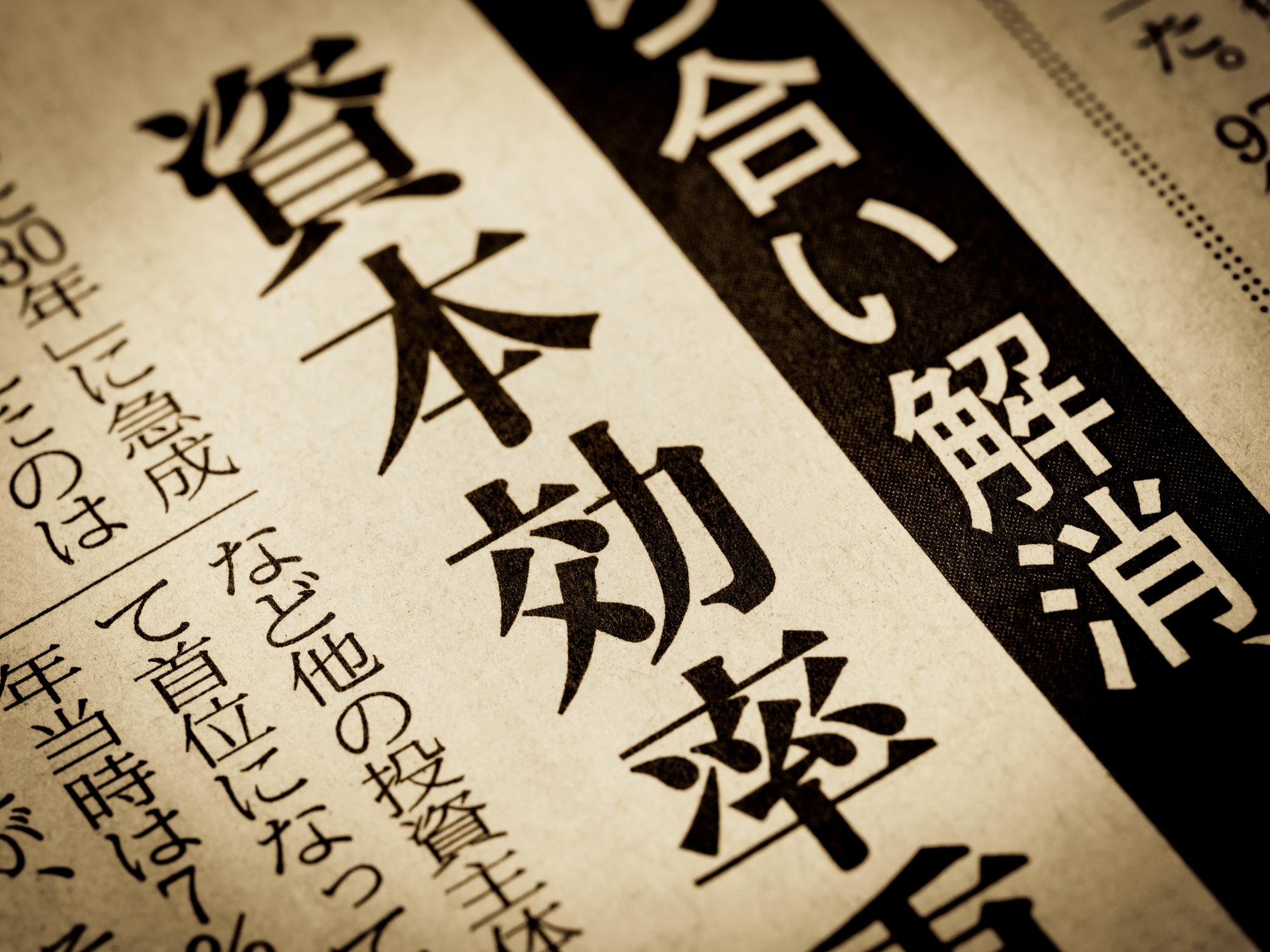
自己株式の消却とは、企業が、市場に流通している自社の株式を株主から買い戻して、消滅させる手続きのことです。別の呼び方として、「自社株消却」「株式消却」という呼び方もあります。具体的にどのような手続きをとればいいのか、自己株式を消滅させることにはどんなメリットがあるのかなどを解説していきます。
M&A・事業承継で失敗したくないなら
ジョブカンM&Aは、経験豊富なアドバイザーが事業の売却・買収をトータルでサポートします。
「信頼できる相手を見つけたい」「交渉や手続きが不安」「適正な価格で取引したい」といった、M&Aに関するあらゆるお悩みを解決に導きます。
詳しいサービス内容を知りたい、気軽に相談したいという方は、下記サービスサイトをご覧ください。
自己株式の取得・焼却・処分とは?
自己株式の消却について深堀するにあたっては、自己株式の取得および処分についても理解を深める必要があります。また、自己株式そのものについてもきちんと理解しておくと理解が深まるので、順を追って解説していきます。
自己株式とは
自己株式とは、株式会社が発行した株式のうち、自社が市場もしくは株主から買い戻して保有している株式のことを意味します。自己株式は、「金庫株」とも呼ばれます。
自己株式と自社株の違い
なお、自己株式は「自社株」とは違います。どのような違いがあるかというと、自社株は、「企業が発行したすべての株式」を意味します。この考えのもと、「自己株式は自社株の一部」ととらえることもありますが、通常、自社株の株主には議決権および配当を受ける権利があるのに対して、自己株式には議決権や配当権が付されていません。
自己株式の取得とは
自己株式の取得とは、企業が発行した株式を自社に買い戻して、自己株式にすることを意味します。
一般的には、上場企業の場合は市場において不特定多数からの購入によって自社株式を取得するケースが多く、非上場企業の場合は特定の株主からの購入によって自己株式を取得するケースが多いです。
自己株式の取得は、かつては法律によって原則的に禁止されており、詳しくは追って説明しますが、「消却」またや「ストックオプション」などの特定目的がある場合に限って認められていました。なぜ禁止されていたかというと、インサイダー取引や株価操縦などを防ぐためです。
しかし、2001年の商法改正によって状況は一変。自己株式の取得が「原則禁止」から「原則自由」へと切り替えられたことで、無制限かつ無期限の保有が認められるようになったのです。しかも現在では、スピーディに自社株式の買取をおこなうこともできます。
ただし、一日に注文できる数量や値段は制限することによって、インサイダー取引や株価操縦などを防ぐための対策も取られています。
自己株式の消却とは
自己株式の消却とは、企業が市場または個人から買い戻した株式を消滅させて、株式を無効化させることです。
つまり、買い戻した後に消滅させることになるので、取得と焼却は一連の手続きであるということになります。
自己株式は、「株式消却」「自社株消却」と呼ばれることもあります。
なお、何のために消滅させるかというと、発行済株式総数を適正化させるためです。つまり、自社が所有している自己株式を消滅させることによって、発行済株式総数を減少させるというわけです。これによって、市場に流通する株式数が減り、1株あたりの純利益(EPS:Earnings Per Share)が高まるため、株価の上昇が期待できます。
自己株式の処分とは
自己株式の処分とは、企業が所有している自己株式を売却することを意味します。
先に解説した自己株式の消却との違いは何かというと、自己株式の処分のほうは売却であるため「買い手がいる」ということになるので、発行済株式総数が減少しません。
では、なぜ自己株式を処分するのかというと、売却によって得た利益を資金調達や企業再編などに活用するためです。
M&A・事業承継で失敗したくないなら
ジョブカンM&Aは、経験豊富なアドバイザーが事業の売却・買収をトータルでサポートします。
「信頼できる相手を見つけたい」「交渉や手続きが不安」「適正な価格で取引したい」といった、M&Aに関するあらゆるお悩みを解決に導きます。
詳しいサービス内容を知りたい、気軽に相談したいという方は、下記サービスサイトをご覧ください。
自己株式を消却するメリット
ここからは本題の、自己株式の消却について掘り下げていきます。まず、自己株式を消却するメリットは次の通りです。
それぞれ詳しくみていきましょう。
発行済株式総数の適正化
先に解説した通り、自己株式を消却することによって発行済株式総数を減少させることは、発行済株式総数の適正化につながります。発行済株式総数が適正化されることがなぜメリットかというと、発行済株式総数が多いとそのぶん株主が増えることから、経営に関する意思決定に時間がかかる一方、発行済株式総数が適正化されると意思決定がスムーズにおこなわれるようになるためです。
株主への利益還元
こちらも、先に解説した通りですが、自己株式の消却によって市場に流通する株式数が減ると、1株あたりの純利益(EPS)が高まります。そうなると、株主の資産が増加するということになるため、買い動向が強まり、株価の上昇が期待される好循環を生むことがあります。
敵対的買収の防止
もうひとつのメリットは、相手の同意を得ずに株式を多く買い占める「敵対的買収」を防げる点にあります。市場から株式を買い戻して市場に出回っている株数が減れば、敵対する会社が株式を取得するためには、多額の購入資金が必要となるため、購入のハードルが上がり、買収される可能性が低くなります。
自己株式を消却するデメリット
続いて、デメリットとしては次の点が考えられます。
それぞれ詳しくみていきましょう。
自己資本比率の低下
先に述べた通り、自己株式の消却をおこなうためには、まず、自己株式を取得する必要があります。自己株式の取得とは、企業が発行した株式を自社に買い戻すことであり、当然お金がかかるため、「企業の自己資金が減少する」ということになります。
自己株式を取得するために自己資金を使うと、貸借対照表の純資産が減少するため、財務の健全性を示す「自己資本比率(ROE:Return On Equity)」が低下します。
なお、自己資本利益率(ROE)は、「当期純利益(最終的な利益)÷自己資本(自社が保有する資金のうち返済の必要がない資金)」で計算します。
自己資本利益率(ROE)の数値が高いと、「資本を効率よく使って稼いでいる」ということになり、投資価値がある企業とみなされるので、自己資本利益率(ROE)の低下はネガティブ要素ということになります。これによってどのようなことが起こり得るかというと、財務面に問題があるとみなされることから、株価が伸び悩んだり、金融機関からの信用を失ったりする可能性が高まります。
資本繰りの悪化
市場から買い戻した自己株式は、原則として市場で売却したり第三者に譲渡したりすることができません。その結果として、資金繰りが悪くなる可能性が無きにしも非ずです。
資金繰りが悪化すると、新たに事業を立ち上げたり、新しい設備を導入したりすることが難しくなる場合があります。
M&A・事業承継における自己株式消却の戦略的活用
自己株式の取得・消却は、M&Aや事業承継の場面で戦略的に活用されることがあります。
売り手側の活用法
事業承継を円滑に進めるため、後継者以外の親族や従業員などが保有する株式を会社が買い取り、消却することがあります。特に非上場企業の場合、創業者や親族が株式を分散して保有しているケースが多々あります。後継者が経営権を安定させるためには、会社が株主総会の特別決議**を経て、後継者以外の株式を買い取る手法がよく用いられます。この際、みなし配当の課税問題が売り手(株主)にとって最大の注意点となります。
「みなし配当」とは? 自己株式取得における税務上の注意点
自己株式の取得は、会計上は資本取引ですが、税務上は異なります。特に株主(売り手)にとっては、受け取る対価が「株式の譲渡対価」と「みなし配当」の2つに分解される点に注意が必要です。
みなし配当とは、会社から受け取る自己株式の対価のうち、その株式に対応する「資本金等の額」を超える部分を指します。この「みなし配当」に該当する金額は、株式の譲渡所得(税率約20%)ではなく、配当所得として総合課税の対象となります。
株主の所得によっては税率が最大で55%近くなる可能性があり、手取り額が大きく変わるため、特に非上場会社が特定の株主(創業者や親族など)から株式を買い取る際には、事前に税理士に相談することが不可欠です。
M&Aデューデリジェンスにおける自己株式のチェックポイント
財務デューデリジェンス
法務デューデリジェンス
自己株式を取得する手続き
続いては、自己株式消却の前段階として必要な、自己株式取得の手続きをみていきます。
なぜ、自己株式消却の前段階として自己株式取得が必要かというと、会社法では、消却できる株式は自己株式に限定されているため、自己株式の消却をおこなうためには、当該株式の所有する自己株式を取得することが前提となるためです。
自己株式を取得する方法は、先に解説した通り、一般的には、上場企業の場合は市場において不特定多数からの購入によって自社株式を取得するケースが多く、非上場企業の場合は特定の株主からの購入によって自己株式を取得するケースが多いです。
不特定多数から取得する場合、株主総会の普通決議をおこないます。株主総会の普通決議では、出席議決権の過半数の賛同を得ることができれば、議決されることになるため、不特定多数からの購入が可能となります。
特定の株主から取得する場合、株主総会の特別決議をおこないます。株主総会の特別決議においては、出席議決権の2/3以上の賛同を得ることができれば議決され、購入が可能となります。
自己株式の取得にかかる制限
自己株式を取得する際は、「財源規制」に注意する必要があります。自己株式取得における財源規制とは、自己株式の買取に設けられた上限のことです。具体的には、“買取時点における分配可能額の範囲内”でのみ、自社株を買い取ることが可能となります。
分配可能額の計算は簡単ではありませんが、「その他資本剰余金の額+その他利益剰余金の額」によって大まかな金額は出ます。
ただし、次のケースにおいては、自己株式取得において財源規制は設けられません。
M&A・事業承継で失敗したくないなら
ジョブカンM&Aは、経験豊富なアドバイザーが事業の売却・買収をトータルでサポートします。
「信頼できる相手を見つけたい」「交渉や手続きが不安」「適正な価格で取引したい」といった、M&Aに関するあらゆるお悩みを解決に導きます。
詳しいサービス内容を知りたい、気軽に相談したいという方は、下記サービスサイトをご覧ください。
自己株式を消却する流れ
続いては、自己株式を消却する流れをみていきましょう。自己株式を消却する流れは次の通りです。
それぞれ詳しくみていきましょう。
自己株式を取得する
前述の通り、自己株式を消却するにはまず、自己株式を取得する必要があります。
消却する自己株式の数を決める
自社が自己株式として保有している株式数を、株式名簿を通して確認して、そのうち何株を消却するのかを決めます。なお、「種類株式発行会社」の場合は、自己株式の種類および種類ごとの数量を決定する必要があります。
登記簿謄本、定款を用意する
取得から3か月以内の登記簿謄本、最新の定款を用意する必要があります。登記簿謄本、定款ともに複写でも可能です。
取締役会などの決議機関で消却決議をおこなう
自己株式の消却決議は、取締役会などの決議機関によっておこなわれます。なお、自己株式の消却にかかる決議内容は、会社法第178条によって次のように定められています。
会社法第178条
1. 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない
2. 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない
なお、取締役会設置会社の場合、決議機関は取締役会による決議となりますが、取締役非設置会社の場合、株主総会の普通決議か、もしくは取締役の過半数の議決が必要となります。
株式失効の手続きをとる
株式の消却を実行したら、株式失効の手続きをおこないます。具体的な手続き内容は、株式名簿の修正です。なお、株券発行会社の場合は株券を破棄する手続きをおこなうことが必要です。
株式総数減少の変更登記申請をおこなう
自己株式を消却すると、会社の発行済株式総数が減少するため、
会社法第915条第1項、第911条第3項第9号によって、効力発生日から2週間以内に変更登記をおこなうことが定められています。
効力発生日とはなにかというと、自己株式の消却が決議された後、会社が次の行為をおこなって消却する自己株式を特定した日を指します。
登記変更に必要な記載内容や添付書類などは次の通りです。
【主な申請事項】
登記の事由(例 株式の消却)、登記すべき事項(変更日付など)、発行済株式の総数など
【申請時に添付が必要な書類】
取締役会議事録(非設置会社の場合は取締役の決定書)、委任状(代理人依頼の場合)など
【必要経費】
自己株式取得時・消却時・処分時の会計処理
続いては、自己株式取得時・消却時・処分時の会計処理を解説していきます。
自己株式取得時の会計処理
自己株式を取得した際の勘定科目は、純資産に属する「自己株式」となります。
貸借対照表には、株主資本の控除項目として表示されます。
(例)自己株式1,500,000円を現金で取得した場合
| 借方 | 貸方 |
| 自己株式 1,500,000円 | 現金 1,500,000円 |
自己株式消却時の会計処理
自己株式を消却した際、その帳簿価額をその他資本剰余金から減額するのが原則です。しかし、その他資本剰余金の残高が不足している場合は、その不足分をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する処理が必要となります。
(例)保有している自己株式500,000円を償却した場合
| 借方 | 貸方 |
| その他資本剰余金 300,000円 | 自己株式 500,000円 |
| その他利益剰余金 200,000円 |
自己株式処分時の会計処理
ついでに、自己株式を処分した場合の会計処理も解説していきます。
自己株式を処分すると、保有している自己株式と売却価格に差額が生じます。この差額は、帳簿価格より安く売れた場合は「自己株式処分差損」、帳簿価格より高く売れた場合は「自己株式処分差益」で処理します。「自己株式処分差損」「自己株式処分差益」は「その他資本剰余金」あるいは「その他利益剰余金」の科目になります。ただし、「自己株式処分差損」の場合において、「その他資本剰余金」から控除しきれない場合、「繰越利益剰余金」で処理しても問題ありません。
(例)帳簿価格500,000円の自己株式を600,000円で処分して、代金は当座預金口座に振り込まれた場合
| 借方 | 貸方 |
| 当座預金 600,000円 | 自己株式 500,000円 |
| 自己株式処分差益 100,000円 |
自己株式消去に関するFAQ
続いては、自己株式消却に関するよくある質問とその答えを解説していきます。
Q. 自己株式の消去と新株発行を同時におこなうことはできますか?
自己株式の消去と新株発行を同時におこなうことは可能です。消去と発行は別の会社法上のって続きですが、同一の株主総会や取締役会で決議して、同日に効力を発生させることも可能です。しかも、資本政策上、よくある手法です。
ただし、自己株式を消去して株数が減少すると、通常は既存株主の持ち分比率が上昇しますが、同時に新株発行をおこなうと、比率が再度変動することになります。
また、先に解説した通り、自己株式を消却すると1株当たりのEPSなどが上がり、株主に還元される一方、新株発行には、資本調達や第三者割当による資本提携という意味合いがあるため、両者を組み合わせることによって、既存株主への還元と新規株主の受け入れを同時に実現できます。
Q. 自己株式の消却をおこなった際、会計において、「自己株式消却損益」という勘定科目は使いますか?
結論から言うと、自己株式の消却においては、「自己株式消却損益」という勘定科目を使うことはありません。
なぜかというと、まず、自己株式は取得した時点で純資産の控除項目として「自己株式」勘定で処理されます。消却時には、その「自己株式」勘定を流し込むだけで、損益計算書には影響しません。つまり、損益勘定は何も流れず、資本の部内での振替処理にとどまるということになります。
Q. 自己株式消去の手続きに費用が掛かった場合の仕訳はどうすればいいですか?
自己株式の消去をおこなうにあたっては、公告費用、登記費用、印紙代、司法書士や弁護士などの専門家報酬といった付随費用が発生する場合があります。これらは、自己株式の消却のために必要な支出ではありますが、会計上は自己株式の帳簿価額や資本剰余金に含めず、発生時の費用処理とするのが原則です。
自己株式の消去を理解するには、体系的な理解が不可欠
自己株式の消去を理解するためには、まず、自己株式の取得について理解する必要がありますし、取得・消去・処分の会計処理の違いについても理解することが不可欠です。しかし、自己株式の取得・消去または処分などを実際におこなうとなると、さらに多くのことを知っておく必要がありますし、体系的な理解が欠かせません。そのため、付け焼刃の知識で実践に移すことはリスクが大きいと考えられます。適切な専門家のサポートを受けることで、リスクを減らして、効率よく手続きを進めていってくださいね。
M&A・事業承継で失敗したくないなら
ジョブカンM&Aは、経験豊富なアドバイザーが事業の売却・買収をトータルでサポートします。
「信頼できる相手を見つけたい」「交渉や手続きが不安」「適正な価格で取引したい」といった、M&Aに関するあらゆるお悩みを解決に導きます。
詳しいサービス内容を知りたい、気軽に相談したいという方は、下記サービスサイトをご覧ください。
この記事は、時点の情報を元に作成しています。

執筆 ジョブカンM&A編集部
ジョブカンM&Aは、株式会社DONUTSが運営するM&Aアドバイザリーサービスです。主に企業の事業承継、成長戦略、出口戦略(イグジット)といった多様なニーズに応えることを目的としています。最大の特徴は、累計導入社数20万社以上を誇るバックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」の広範なネットワークを活用している点です。この強力な顧客基盤を生かし、効率的なマッチングを実現します。
他の関連記事はこちら



