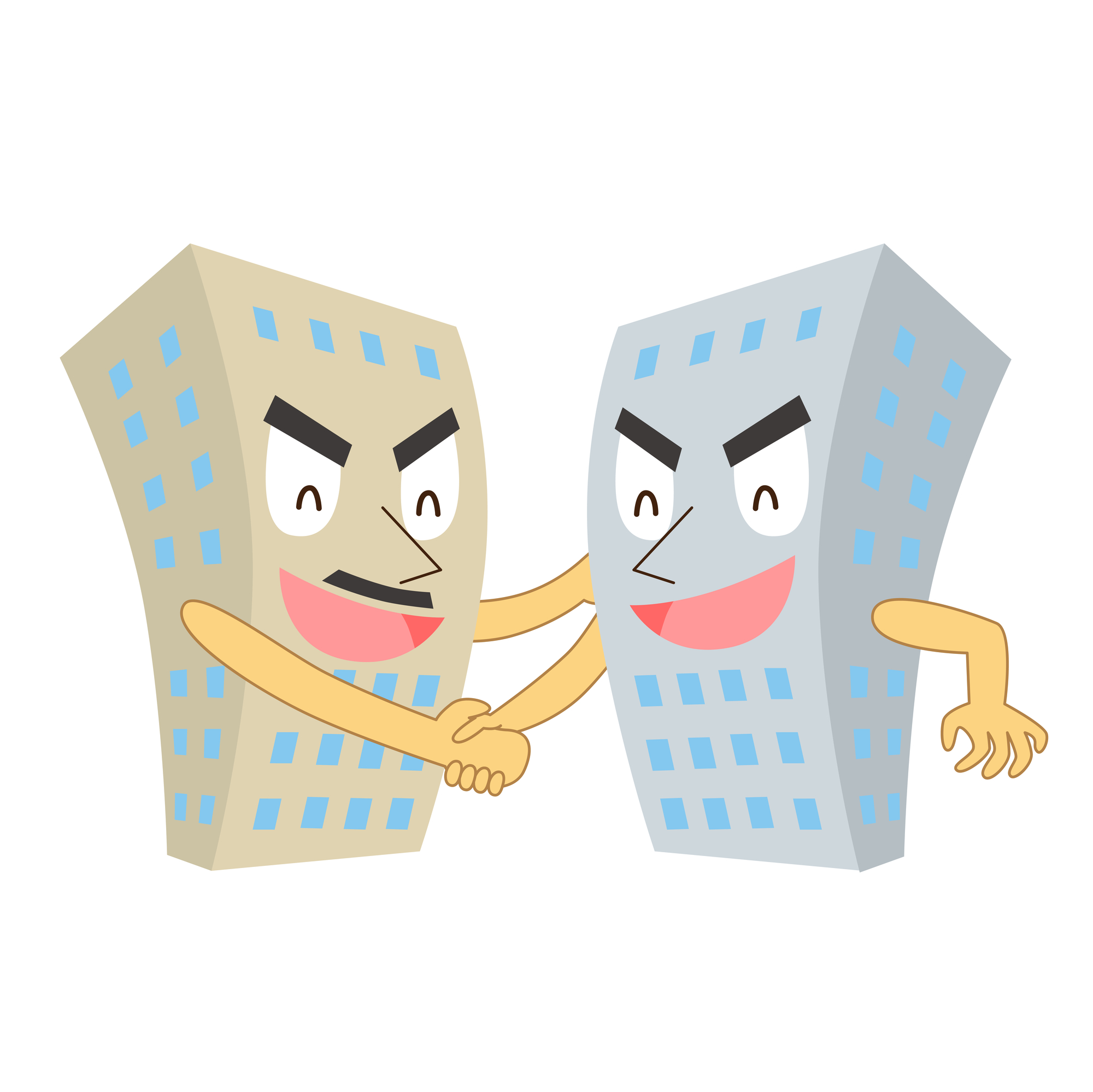
株式会社を家族に引き継ぐには、経営者の保有している株式を、後継者となる家族に譲渡する必要があります。譲渡方法は、「相続」「贈与」「売買」の3種類に大別されますが、それぞれにメリット・デメリットがあり、どの方法が自社にとって最適かは、税金や承継のタイミング、会社の現状によって大きく異なります。
本記事では、この3つの譲渡方法について、基本的な流れや特徴、注意点を具体的に解説します。さらに、税務上のリスクを避け、最も効率的に事業承継を進めるための重要なポイントを網羅的にご紹介します。
M&A・事業承継で失敗したくないなら
ジョブカンM&Aは、経験豊富なアドバイザーが事業の売却・買収をトータルでサポートします。
「信頼できる相手を見つけたい」「交渉や手続きが不安」「適正な価格で取引したい」といった、M&Aに関するあらゆるお悩みを解決に導きます。
詳しいサービス内容を知りたい、気軽に相談したいという方は、下記サービスサイトをご覧ください。
株式を家族に譲渡する3つの方法
まずは、「相続」「贈与」「売買」の3種類がどんな方法であるのかを解説していきます。
相続
| 相続のメリット | ・遺言書で後継者と株式の割合を明確に指定できていれば、法定相続人間のトラブルを防げる可能性が高い ・基礎控除を活用することで、相続税の負担を軽減できる可能性がある(株式を含めて受け継いだ財産の総額が基礎控除範囲内に収まる場合、相続税を納める必要もない) |
| 相続のデメリット | ・経営者の死亡に伴う株式移転であるため、いつ移転することになるのかがわからない ・遺言書の作成手続きが間に合っていなければ、後継者以外の法定相続人に株式が渡り、経営権の承継が難しくなる可能性がある ・後継者以外の法定相続人が「遺留分侵害額請求」をおこなった場合、経営権が分散して企業経営に影響を及ぼす可能性がある ・法令に沿った正式な形式でない遺言書は、無効となるリスクがある |
相続は、経営者が死亡した場合に発生する株式の移転です。経営者の遺言をもとに、後継者に株式が引き継がれることになります。遺言書を作成するにあたって、経営者は後継者との協議や、相続の内容に関する取り決めを事前におこなう必要があります。ただし、遺言書を作成するにあたっては、法定相続人に認められる最低限の取り分である「遺留分」に配慮することが大切です。なぜかというと、法定相続人には遺留分を自らの受取分として主張できる権利があるため、法定相続人の遺留分を侵害する内容の遺言書であると、遺留分侵害額請求を行使される可能性があるためです。
なお、「遺留分侵害額請求権」は、以前は「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、法改正によって、2019年7月1日以降に亡くなった方の相続からは、「遺留分侵害額請求権利」と呼ばれるようになりました。
また、適切な遺言書が準備できていないまま経営者が死亡した場合、後継者以外の法定相続人に株式が相続される場合があります。
相続によって株式が後継者に引き継がれる場合、相続税が課されることとなり、株式を含む相続財産価額のうち、基礎控除額となる「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた部分に対して、税率が適用されることとなります。
贈与
贈与とは、後継者に無償で株式を譲渡する方法です。株式を譲受する側が、株式を買うための資金を用意する必要がないため、譲受側の負担が少ないのが特徴です。ただし、贈与税がかかるため、株価対策をおこなうことが大切です。
贈与は、「生前贈与」「遺贈」「民事信託」の3種類にわけることができます。
生前贈与
| 生前贈与のメリット | ・年間110万円までの譲渡であれば贈与税がかからない ・「相続時精算課税制度」を活用することで2,500万円まで非課税で譲渡できる ・贈与者が存命中に後継者を指定して株式譲渡を開始できるため、相続よりも経営者の意思を反映させやすい |
| 生前贈与のデメリット | 生前贈与した財産は、贈与者が贈与後7年以内に死亡した場合、贈与した株式の一部は相続税の課税対象となる(2024年1月1日以降) |
生前贈与とは、贈与者が生きている間におこなう贈与のことです。生前贈与には特別な様式は存在せず、口頭でも成立します。
生前贈与をおこなう場合、年間110万円まで非課税となる「暦年課税」や、2,500万円まで非課税で一括贈与できる「相続時精算課税制度」を活用することができます。ただし、贈与後7年以内に贈与者が死亡した場合、贈与した株式の一部は相続税の対象となるため注意が必要です。
とはいえ、7年以内に自分が死ぬかどうかは誰にもわからないことですが、そうなる可能性を少しでも減らせるよう、“生前贈与はできるだけ早めにおこなう”という対処法をとる以外ありません。
遺贈
| 遺贈のメリット | ・遺言書を作成するため、相続人同士で揉め事が起きるのを回避することができる ・相続人それぞれに株式を与える割合を指定できる ・法定相続人以外の親族にも財産を贈ることができる |
| 遺贈のデメリット | ・遺言書を作成する必要がある ・遺言書の書き方などに間違いがあった場合、無効となる可能性がある ・相続人が相続を放棄した場合、他の相続人間で争いが起きる可能性がある |
遺贈とは、遺言書によって財産を贈与することです。つまり、贈与者が亡くなった後に株式が後継者に渡ることになります。
遺言書が必要だという点は相続と同じですが、相続の相手は法定相続人でなければならない一方、贈与の相手は法定相続人でなくても構いません。また、遺贈のための遺言書は、法令で定められた所定の様式のもので作成されている必要があります。
また、遺贈のための遺言書には、相続のための遺言書とは異なり、遺言者の一方的な意志が表示されるため、相続人が相続を放棄する可能性もあります。
民事信託
| 民事信託のメリット | ・受益者の設定や事業承継実行の条件などに関して、経営者の意向を反映させられる ・経営者の死去に伴い、自動的に経営権が後継者に移るため空白期間ができない |
| 民事信託のデメリット | ・経営者が存命中に事業承継することができない ・遺留分侵害額請求権を行使された場合の明確な対処法が決まっていない |
民事信託とは、信頼できる知人や親族などを受託者として、信託契約を締結する制度のことです。なお、「信託」とは、財産の管理や処分をおこなうことで、委託者は自分に判断能力がある間に受託者と契約を締結します。
家族を受託者として民事信託を活用する場合、「家族信託」となります。
なお、家族信託を実施したことで遺留分侵害額を請求された場合、対処法が明確に定まっていないため、請求を却下できない可能性があります。
売買
| 売買のメリット | ・資金力のない後継者候補が介入することを防ぎやすい ・売買した株式に関しては遺留分侵害額請求から除外できる |
| 売買のデメリット | ・後継者が株式価格に相当する資金力を有している必要がある
・時価よりも著しく低い価格で株式を売買した場合、時価との差額が贈与とみなされ、後継者に贈与税が課されるリスクがある。適正な時価を算定し、その価格で売買契約を結ぶことが不可欠である ・売買によって得た利益に譲渡所得税が課される |
家族間であっても、株式を売買するケースがあります。家族であることを考慮した金額設定にして、その金額が時価と乖離している場合、贈与税が課せられる可能性があるので注意が必要です。
家族間の株式譲渡で発生する税金
続いては、家族間の株式譲渡において税金がかかるパターンとその計算方法を解説していきます。
贈与税
生前贈与によって株式譲渡をおこなう場合、先にも解説した通り、課税年度ごとに、基礎控除額110万円を超えた部分に対して贈与税が課されます。逆にいうと、110万円までは非課税となります。
また、贈与税申告の際、暦年贈与から相続時精算贈与に切り替えることも可能です。相続時精算課税は、基礎控除の額が課税年度ごとではなく「相続時までの贈与の総額」で計算されます。最大2,500万円まで非課税で、2,500万円を超えた部分に対しての税率は、一律20%と決められています。
暦年贈与と相続時精算課税の比較は次の通りです。
| 暦年贈与 | 相続時精算課税 | |
| 対象となる贈与 | 相続時精算課税を選択しなかった贈与 | 60歳以上の直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与 |
| 基礎控除額 | 毎年110万円 | 最大2,500万円 |
| 税率 | 課税価格によって10~55% | 20% |
| 相続絵時の課税対象 | 相続開始以前の7年間 | 制度選択後のすべての贈与 |
| 相続税課税時の評価 | 相続開始時点の時価 | 贈与時点の時価 |
| 事業承継税制 | 併用化 | 併用化 |
なお、事業承継税制とは、相続税・贈与税の納税猶予が受けられる制度です。また、制度利用後、一定期間にわたって要件を満たすと、猶予された税額が免除されることになります。
相続税
先に述べた通り、相続によって株式が後継者に引き継がれる場合、株式を含む相続財産価額に相続税が課されることとなります。相続税の税率は、取得した価額に応じて、次のように段階的に決められています。
| 課税価格 | 税率 |
| 1,000万円以下 | 10% |
| 3,000万円以下 | 15% |
| 5,000万円以下 | 20% |
| 1億円以下 | 30% |
| 2億円以下 | 40% |
| 3億円以下 | 45% |
| 6億円以下 | 50% |
| 6億円以上 | 55% |
また、これも先に述べた通りですが、株式を含む相続財産価額のうち、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」は基礎控除の対象となるため、相続財産価額がこの範囲内であれば相続税がかからないということになります。
参照:政府広報オンライン「相続税はいくらから?基礎控除とは?相続税の基本を確認!」
譲渡所得税
譲渡側の生前に売買によって株式譲渡がおこなわれた場合、譲渡者が受け取った売却対価から取得費および委託手数料などを引いた譲渡益に対して、譲渡取得税が課されます。譲渡取得税の税率は、所得税15%、住民税5%の合計20%ですが、2037(令和19)年までに関しては、時限措置として復興特別所得税0.315%も加味されるため、合計税率は20.315%になります。
株式を家族に譲渡する際の流れ
続いては、「相続」「贈与」「売買」の3種類それぞれの方法で、株式を家族に譲渡する際の流れをみていきます。
相続の流れ
相続によって株式を譲渡する場合、遺言執行もしくは遺産分割協議を経て、株式名簿を書き換えることによって手続きが完了となります。
有効な遺言がある場合
有効な遺言がある場合は、遺言執行によって株式を含む財産の取得が実現します。ただし、先に述べた通り、遺留分侵害額請求権が行使される可能性はあります。
有効な遺言がない場合
有効な遺言がない場合は、法定相続人が集まって遺産分割協議をおこないます。協議によって合意が成立したら、各人の実印による署名捺印がある遺産分割協議書を作成することによって、株式名簿の書き換えとその他の手続きを開始できます。
株式名簿を書き換える
遺言または遺産分割協議によって株式の取得者が決まったら、発行会社に相続について通知をおこない、株式の名義書き換え請求をおこないます。保護預かり口座に株券がある場合、株式名簿の作成などを受託している信託銀行や証券代行会社をはじめとする、株式名簿管理人に依頼するのが一般的です。
贈与の流れ
贈与によって株式を譲渡する場合、贈与税が課されることを考慮して、株式を正しく評価するプロセスを踏むことが大切です。
株式を正しく評価する
まずは、株式を正しく評価します。上場株式の場合、次のうちもっとも低い価格を「課税評価額」とします。
非上場株式の場合、会社の規模によって3段階分類する「原始的評価方式」か、1株当たりの配当金を一定の利益(10%)で割り戻して株価を算出する「特例的評価方式」のいずれかで評価することになります。
贈与契約書を作成する
贈与は口頭でも成立しますが、適正申告のための根拠を書面で残す必要性があることや、贈与を巡って発生する可能性のある親族間トラブルを防止することを考えると、株式価格決定後に「贈与契約書」を作成しておくことが望ましいといえます。
贈与契約書の形式に決まりはありませんが、次の項目は記載しておくといいでしょう。
株式の名義を書き換える
贈与契約書に双方の署名捺印が済んだら、株式の名義を変更します。なお、暦年贈与の基礎控除の範囲内で譲渡し続ける場合、税法上、「定期贈与」の扱いになる可能性があります。定期贈与とは、あらかじめ贈与の総額を決めたうえで、定期・定額で譲渡し続ける贈与のことです。定期像とであるとみなされた場合、最初に贈与した課税年度にまとめて課税対象とされるため負担が大きくなります。
売買の流れ
売買によって株式を譲渡する場合、譲渡制限の有無に注意することが大切です。
株式の譲渡制限の有無を確認する
まずは、譲渡制限の有無を確認します。譲渡制限がある場合、発行会社から承認を得なければ取引できません。承認を得るには、譲渡人単独もしくは譲受人と譲渡人が共同して、発行会社に対して「譲渡承認請求」をおこないます。譲渡承認請求においては、譲渡の対象となる株式の種類と数のほか、譲渡先の氏名・名称を明らかにする必要があります。
株式譲渡の承認決議を得る
株式譲渡承認請求を受けた発行会社では、取締役会設置会社の場合は「取締役会」、そうでない会社の場合は「株主総会」において、請求を承認するかどうかを決めることになります。ただし、定款で承認期間を株主総会と定めている場合は、取締役会が設置されていても、承認するのは株主総会となります。
株式譲渡の通知をおこなう
株式譲渡承認請求を受けた発行会社は、請求を受けて2週間以内に、株式譲渡の承認請求を受けたことを通知しなくてはなりません。2週間以内に通知がおこなわれない場合、「承認」とみなされます。ただし、請求者と発行会社の同意があれば、通知期限を変更することができます。
株主譲渡契約をおこなう
発行会社の承認などの条件が整ったら、家族間で売買契約を結んで、譲渡価格を家族間で決定します。口頭で合意した場合も売買成立になりますが、税申告などに関するトラブルを避けるためにも、契約書を作成するのが一般的です。売買契約書には、当事者の名前や売買成立日、株式の数、譲渡日、譲渡対価、支払期限などを記します。
株主名簿の書き換え請求をおこなう
株主名簿の書き換え請求をおこなったら、「株主名簿記載事項証明書」の交付請求もおこなって、実際に株主が変更されているかを確認しましょう。
家族間での株式譲渡に関するFAQ
続いては、家族間での株式譲渡に関してよくある質問とその答えを紹介していきます。
Q. 家族への株式譲渡は、どのような場合に検討すべきですか?
家族への株式譲渡は、事業承継を考えているとき、もしくは相続税の節税を図りたいとき、議決権をコントロールしたいときなどに実施されるケースが多いでしょう。また、相続によって株式が複数の相続人にわかれて、会社運営に支障が出るのを防ぐためにおこなわれることもあります。
Q. 非上場株式の評価は自分でもできますか?
非上場株式の評価を完全に自分でおこなうことは非常に難しいと考えられます。なぜかというと、非上場株式には市場価格が存在しないため、国税庁の「財産評価基本通達」に基づいて評価する必要がありますが、この評価方法を理解するためには専門的な知識が不可欠であるためです。
なお、非上場株式の評価は、主に以下の2つの方式を会社の規模に応じて使い分けます。
類似業種比準方式
会社の「配当」「利益」「純資産」を、同業種の上場企業と比較して株価を算出する方法です。
純資産価額方式
会社の資産から負債を差し引いた純資産額をもとに株価を算出する方法です。
なお、国税庁の通達に沿って理論的に計算すること自体は可能といえば可能ですが、評価に誤りがあると、贈与税や相続税の課税リスクが高まります。そのため、実務においては税理士に依頼するのが得策であるといえます。
Q. 贈与後に売却した場合、譲渡所得税はどうなりますか?
贈与された株式を受贈者が売却した場合、譲渡所得税が発生します。この際、重要になってくるのが「取得費の引き継ぎ」と「取得時期の引き継ぎ」という贈与特有のルールです。
具体的には、取得費と取得時期は贈与者から引き継ぐ必要があるとされているため、取得費に関しては、贈与者が購入・取得したときの費用をそのまま引き継ぐことになります。取得時期に関しては、贈与者が取得した日が基準とされることになります。
つまり、贈与を受けた人が売却した場合、もともと贈与者が安く取得していた場合などがあるため、取得費が低く、譲渡所得が大きくなりやすいということになります。
Q. 株式を家族に譲渡・贈与する場合と、家族以外に譲渡・贈与する場合の違いは?
株式を家族に譲渡・贈与する場合と、家族以外に譲渡・贈与する場合の主な違いは次の通りです。
| 家族への譲渡・贈与 | 家族以外への譲渡・贈与 | |
| 贈与税 | 一定条件で特例税率(特別贈与)適用。中長期的節税が可能 | 一般贈与税率で課税。税率が高くなりがち |
| 譲渡所得税(売買の場合) | 売買なら原則課税(時価と売買価格に差があるとみなされる) | 同様に課税。ただしみなし譲渡の判断がより厳しい傾向。 |
| 時価と取引価格の乖離 | 税務署もある程度「目的(事業承継)」を考慮しやすい | 家族以外だと不自然な安値譲渡は贈与とみなされやすい |
| 会社法上の取り扱い(譲渡制限株式) | 譲渡制限があっても承認されやすい傾向にある | 原則として株主総会等で承認が必要。拒否される可能性もある |
| 事業承継税制の活用 | 適用 | 適用対象外 |
| 議決権の集中・支配構造の維持 | 安定的な株主構成を維持しやすい。 | 株主構成が分散・不安定化しやすい |
| 遺留分対策 | 他の家族の相続権に配慮が必要。生前贈与加算あり | 家族以外だと遺留分侵害額請求のリスクが特に高い |
どの方法での株式譲渡がもっとも効率的かは専門家に確認が必須
家族間で株式譲渡をおこなうには、前述の通りいくつかの選択肢があるため、自社にとってはどの方法での株式譲渡がもっとも効率的であるかは、専門家に判断してもらうことが大切です。生じる税金、発生し得るトラブルなどいくつかの判断材料をもとに検討していくことになるため、納得のいくかたちで譲渡を進められるよう、早い段階で専門家に相談することを心がけてくださいね。
M&A・事業承継で失敗したくないなら
ジョブカンM&Aは、経験豊富なアドバイザーが事業の売却・買収をトータルでサポートします。
「信頼できる相手を見つけたい」「交渉や手続きが不安」「適正な価格で取引したい」といった、M&Aに関するあらゆるお悩みを解決に導きます。
詳しいサービス内容を知りたい、気軽に相談したいという方は、下記サービスサイトをご覧ください。
この記事は、時点の情報を元に作成しています。

執筆 ジョブカンM&A編集部
ジョブカンM&Aは、株式会社DONUTSが運営するM&Aアドバイザリーサービスです。主に企業の事業承継、成長戦略、出口戦略(イグジット)といった多様なニーズに応えることを目的としています。最大の特徴は、累計導入社数20万社以上を誇るバックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」の広範なネットワークを活用している点です。この強力な顧客基盤を生かし、効率的なマッチングを実現します。
他の関連記事はこちら



